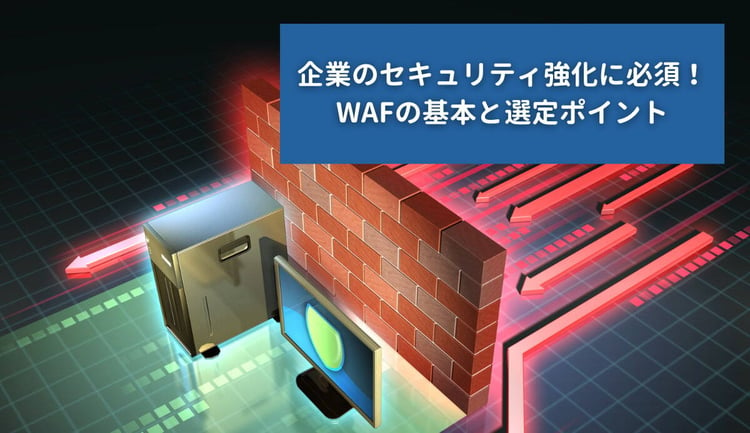クラウド環境が急速に発展する中で、企業のデータセキュリティとプライバシーが常にリスクにさらされています。
このような状況の中、注目されているのがCTEMです。
CTEMは、クラウド資源に対する脅威をリアルタイムで検出し、評価、対処するための包括的なアプローチを提供します。
本記事では、CTEMの基本的なことから、CTEMのメリット、実施フェーズ、活用シーンをご紹介します。
CTEMとは
シーテムと呼ばれる「CTEM」とは「Continuos Threat Exposure Management」の略で、日本語では「継続的脅威露出管理」と訳されます。
Threatが脅威、Exposureが晒す/晒されるという意味なので、脅威に晒されているものを管理するという意味になります。
脅威に晒されているものを継続的に管理し、改善していくというセキュリティの考え方の1つです。
自社への脅威レベルを監視・評価・削減し、それに対する分析と修復方法が適切かどうかを検証していきます。
CTEMのメリットとは
リアルタイムの脅威検出と対応
CTEMは、クラウド環境全体のセキュリティをリアルタイムで監視し、不審な動きや潜在的な脅威を即座に検出します。
これにより、脅威が拡大する前に迅速に対応し、データの損失やシステムダウンを防ぐことができます。
コンプライアンスの強化
多くの業界では、データ保護やセキュリティに関する規制が厳しく設定されています。
CTEMを導入することで、これらの規制要件に自動的に準拠しやすくなり、監査時にも必要なセキュリティ対策が適切に行われていることを証明できます。
セキュリティ運用の効率化
クラウド環境は非常にダイナミックで、設定や使用状況が頻繁に変更されることがあります。
CTEMはこれらの変更を追跡し、セキュリティ設定の不備や改善点を指摘することで、セキュリティチームの作業負荷を軽減し、全体的なセキュリティ運用の効率を向上させます。
CTEMを実施する5つのフェーズ
CTEMを実施するには、以下の5つのフェーズが必要です。
- スコープ設定(Scoping)
- 発見(Discovery)
- 優先付け(Prioritization)
- 検証(Validation)
- 実践(Mobilization)
フェーズ1:スコープ設定
まずフェーズ1は「スコープ設定」です。
サイバー攻撃の対象となる可能性のあるデジタル資産の範囲を決定します。
スコープを決めることで、組織が管理しているドメインやサブドメイン、IPアドレスなどを識別できます。
フェーズ2:発見
次に「発見」フェーズです。
影響を与える可能性のある脅威を特定します。
一般的なセキュリティツールは、フィッシングサイトのような類似ドメインのような脅威を検出できないものがあります。
フィッシングサイトや詐欺的なソーシャルメディアページ、ダークウェブデータの漏洩はかなり重大な脅威であるため、しっかりと網羅しておく必要があります。
フェーズ3:優先付け
フェーズ3は「優先付け」です。
すべての脅威が同じレベルのリスクをもたらす訳ではない為、優先順位付けがCTEMの重要な部分です。
優先順位を付けることで、攻撃が引き起こす可能性のある顕在的なリスクと潜在的なリスクの両方の面から、どの脅威に最初に対処するかを決定できます。
優先順位を付けることは、限られたサイバーセキュリティリソースを最大限に活用できるようにするために重要です。
フェーズ4:検証
フェーズ4は「検証」です。
検証では、脅威から防御するために実装したセキュリティ制御が実際に機能するかを確認します。
ここで、ペネトレーションテスト*やレッドチーム演習**などの実践が役に立ちます。
これらは、脅威アクターが攻撃を実行しようとした時に、導入したツールが効果的に攻撃を阻止できることを検証するのに役立ちます。
*ペネトレーションテストとは、日本語で「侵入テスト」を意味し、システム全体の観点でサイバー攻撃耐性がどのくらいあるかを試す為に、悪意のある攻撃者が実行するような方法に基づいて実践的にシステムに侵入することです。ペンテストと呼ばれることもあります。
**レッドチーム演習とは、攻撃側と防御側に分かれ、攻撃側は対象となるシステム・ネットワークに対して擬似的な攻撃を加え目標の遂行を試み、防御側はその攻撃を検知し対処することでインシデント対応能力を向上させるサイバー演習の一種です。
フェーズ5:準備・実践
最後のフェーズは「実践」です。
まず必要な脅威情報の収集・分析を行います。
次に、分析結果をもとに、適切な対策を企画・設計します。そして、それらの対策を実装し、テストを行うことで、セキュリティレベルを向上させます。
これらのプロセスを繰り返すことで、組織のセキュリティ対策は常に最新の状態を保つことができます。
CTEMの活用シーン
サイバーセキュリティ
サイバーセキュリティの分野では、CTEMを用いて進化し続けるサイバー攻撃と効果的に対抗することが可能になります。例えば、リアルタイムでの脅威分析や対応を行い、予防策を強化したり、早期に問題を検知して対応したりすることで、損害の拡大を防げます。
また、既に発生している脅威が継続的に変化する様子をリアルタイムに把握し、組織に最適な防御手段を検討することも可能です。
コンプライアンス
コンプライアンスにおいても、CTEMは非常に重要なツールとなりえます。例えば、脅威の絶え間ない変化に対応するために、適切な規制やプロセスを作成・維持することが求められます。
これにより、組織全体の安全性を保つための規範の遵守を確認し、必要な修正や改善をリアルタイムで行えるようになります。
コンプライアンスへの対応力を高めるために、CTEMの活用が推奨されます。
リスク管理
リスク管理の分野では、CTEMの活用により、組織が直面する可能性のあるリスクを評価し、対策を講じることが可能となります。
例えば、データ侵害のリスクや、システムダウンのリスクなどに、事前に対策を立てるための情報を得ることができます。
また、リスクの発生した際の対応策を素早く立て、ダメージを最小化するという観点からも、CTEMの活用が期待されます。
事業継続計画
最後に、事業継続計画にもCTEMの活用が考えられます。災害や不測の事態が発生した際に、ビジネスを続けるための計画を立てることが求められます。
CTEMを活用することで、これらのリスクに対してリアルタイムで対応し、事業の中断を最小限に抑えることができます。
強固な事業継続計画を作成・維持するためにも、CTEMの活用がとても重要です。
さいごに
本記事では、CTEMの基本概念や、クラウド環境でのセキュリティ強化におけるその重要性について詳しくご紹介いたしました。
現代のDXが進む中で、企業のクラウド環境は常に多様な脅威にさらされています。
CTEMは、これらの脅威に対して効果的に対応し、組織のセキュリティ体制を継続的に改善するための強力なツールです。
導入から運用までの段階的なプロセスを理解し、各フェーズでの具体的な活動を計画することが、成功への鍵となります。
CTEMを利用することで、リアルタイムの脅威検出と対応、コンプライアンスの強化、セキュリティ運用の効率化など、多くのメリットを得られます。
デジタル資産の保護を考える上で、CTEMは避けて通れない選択肢と言えるでしょう。
セキュリティは1度の設定では完璧にはなりません。
継続的な見直しと改善を行うことが重要です。
今後もCTEMの進化に注目し、最新の脅威に対して最適な防御策を講じていきましょう。
メルマガに登録する
課題解決につながるメールをお届けします
アイ・エス・アイソフトウェアーには、IT課題解決につながる解決策が豊富にあります。お役立ち記事や開催セミナー、サービス、支援事例など様々な情報をお届けします。
個人情報の取り扱いに同意した上で、登録してください。
アイ・エス・アイソフトウェアーは、幅広い業界のお客様との取引実績より、小規模課題から大規模課題まで、様々なIT課題を解決することができます。
データ活用や最新技術の活用といったDXにつながる取り組みを一緒に強化していきませんか?